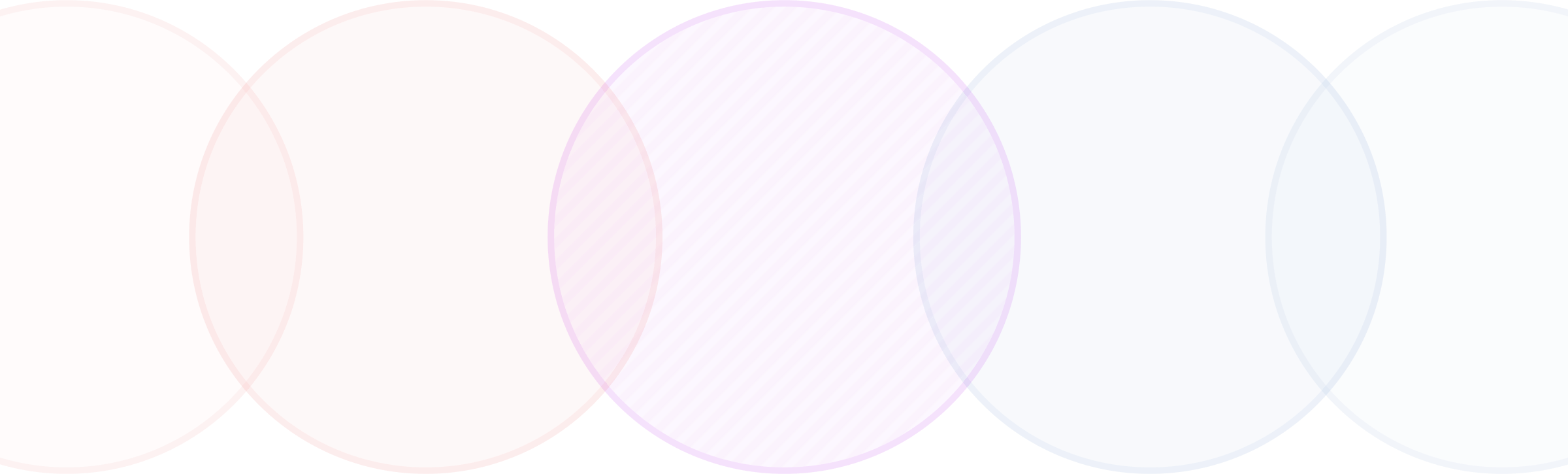
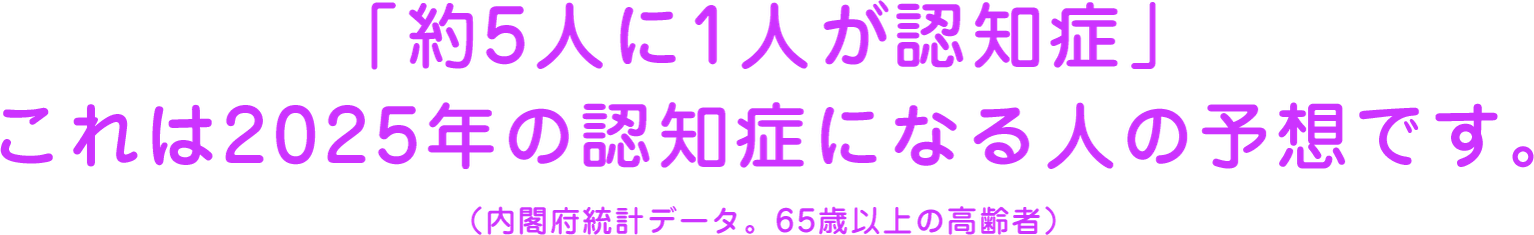
超高齢社会を迎えた日本の
大きな社会課題に対して
私たちがすぐにできることは
認知症を正しく学び、
今から備えることです。
朝日新聞社と
エイベックスグループは
認知症について学び備えるプロジェクト
『リバイバルライフ』を
共同で発足させました。
認知症のご本人の視点で「学び」、
楽しいダンスで
脳と身体を元気にして「備える」ことで、
認知症などの高齢期の課題に対応できる
元気な社会づくりを
支援していきます。
自治体、大学、企業の研修に導入されています。


2024年4月6日
東北ダンスフェスティバル
東北ダンスフェスティバルの特別ゲストとしてTRFのSAMによる「リバイバルダンス スペシャルワークショップ」を開催。来場者と共に、survival dAnceを踊りました。


2024年2月28日
荏原医師会
「荏原医師会 区民向け講演会」にて、「リバイバルダンス」のワークショップを開催しました。


2023年10月2日
国立病院機構 新潟病院
新潟病院オレンジプロジェクトの特別企画「~認知症予防について楽しく知ろう!~」の一環として、リバイバルダンスワークショップの体験会を開催しました。


2023年3月2日
藤沢市
『健康』や『生きがい』をテーマにしたイベント「ふらっと 遠藤!」にて、認知症体験ブースの出展とリバイバルダンスの体験会を行いました。
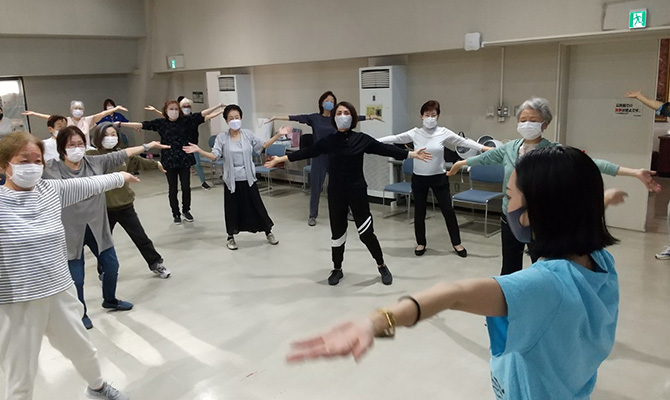

2022年10月23日
熱海市
熱海市民向けのイベントとして、「リバイバルダンスワークショップ」が開催されました。
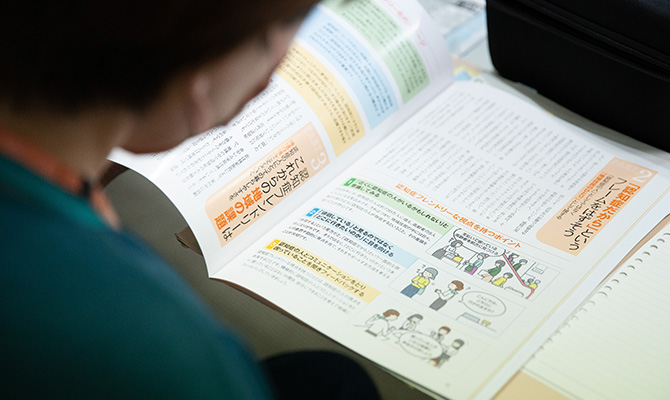

2022年7月23日
伊勢原市
「おやこで認知症サポーター養成講座」の一環として、小学校4~6年生とその保護者を対象に「認知症フレンドリー講座」&「認知症フレンドリーキッズ授業」と「リバイバルダンス」ワークショップを開催しました。

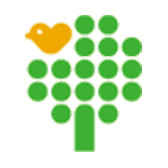
2021年12月11日&18日
のぞみの丘ホスピタル(岐阜県)
認知症疾患医療センターの研修会として、慈恵中央病院との共催にて、リバイバルダンスのワークショップを開催しました。


2021年6月29日&9月17日
伊勢原市
地域包括支援センター職員や認知症地域支援推進員、民生委員向けの研修、および地域住民向けのイベントとして、「認知症フレンドリー講座」と「リバイバルダンスワークショップ」が開催されました。


2021年6月26日
日本認知症予防学会学術集会
第10回日本認知症予防学会学術集会 市民公開講座にTRFのSAM、ETSU、CHIHARUが登壇し、リバイバルダンスのスペシャルワークショップを実施しました。


2021年4月25日
朝日新聞 名古屋本社
愛知県一宮市で開かれた「Reライフ認知症講座」で、朝日新聞読者や地域住民を対象に認知症フレンドリー講座とリバイバルダンスが対面とライブ配信のハイブリッド形式で開催されました。
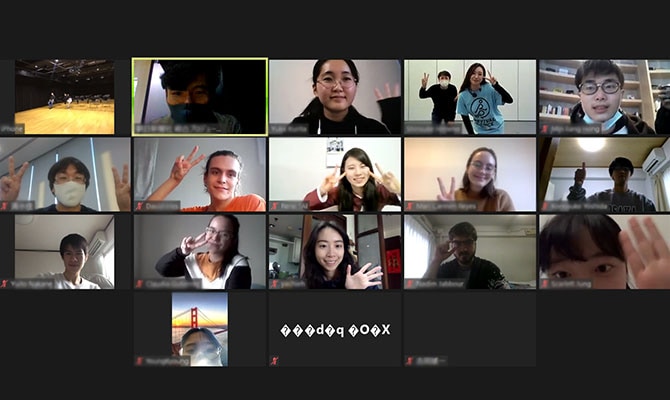

2021年1月19日
大阪大学
大阪大学の留学生向けに「ソーシャルイノベーションとソーシャルデザイン」の授業の一環として、対面とライブ配信のハイブリッド形式で、認知症VR体験会とリバイバルダンスのワークショップを実施しました。


2020年9月19日
藤沢市
「認知症にやさしいまちづくり」に取り組む藤沢市で、高齢者との交流拠点を運営する事業者を対象にした、リバイバルダンスと認知症VR体験会の研修会が開催されました。


2020年1月21日
大阪大学
大阪大学の留学生向けに「ソーシャルイノベーションとソーシャルデザイン」の授業の一環として、リバイバルダンスと認知症VR体験会のワークショップを実施しました。
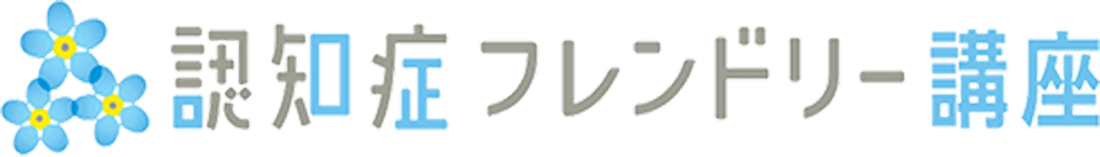
朝日新聞社の「認知症フレンドリー講座」は、
認知症を単なる知識としてだけではなく、
本人インタビューや、専門医の解説、
VRコンテンツなどを活用した体験を通じて、
ご本人の視点から学び、
「認知症の人とともに暮らす社会」の
あり方を考える機会を提供します。

認知症の人のインタビューや専門家の解説動画を通じて、
本人が抱える思いや困り事を知ることから始めます。

認知症になると、「どんな症状が出るのか」「周囲にどう接してほしいのか」「そもそも認知症はどういう病気なのか」を、ご本人の声や専門医の説明から理解することができます。

認知症の人が見えている視点をVRで体験し、認知症をより深く理解することで、認知症を自分事として感じとる機会になります。

最新のVR機器を使って、空間を把握する能力などが低下し、段差が下りづらい感覚を擬似体験できます。

脳科学の専門家、専門医らの監修による、
脳と身体をイキイキさせるリバイバルダンスが誕生!
誰もが知る昭和歌謡*で、おうちで楽しく
ダンスを続けることができます。

脳科学や医学の専門家らの監修と、ダンスの専門家であるTRFのメンバーがそれぞれの知見を掛け合わせ、開発しました。
誰もが知る懐かしの昭和歌謡*を聴きながら、楽しくダンスができます。
※一部、平成に発売した楽曲もあります。

お祭りマンボ(’52)
美空ひばり
プレイバック part 2(’78)
山口百恵
ギャランドゥ(’83)
西城秀樹
お嫁サンバ(’81)
郷ひろみ
survival dAnce ~no no cry more~ (’94)
TRF
太陽にほえろのテーマ(’72)
インストゥルメンタル・カバー
自動車ショー歌(’64)
小林旭
せんせい(’72)
森昌子
川の流れのように(’89)
美空ひばり
年下の男の子(’75)
キャンディーズ
三百六十五歩のマーチ(’68)
水前寺清子

エンターテイメント界のレジェンドダンサーによる、高齢者の運動能力を見極めた知見と、無理なく楽しく踊れる技術を掛け合わせたダンスです。
ご自宅のリビングでDVDを再生しながらご自身でトレーニングをしたり、講師を派遣してのトレーニング(対面またはオンライン)で開催したりすることができます。

ご自宅のリビングで
DVDを観ながらトレーニング

ご指定の場所まで講師を派遣
またはオンライン配信
※権利の都合により一部の楽曲はご提供できません。
青春時代に聞いていた音楽に合わせて踊ることで、気持ちも若返ったように感じました。ダンス部分も楽しかったのですが、ウォーミングアップは身体を動かすだけではなく脳のトレーニングにもなり、非常に良かったです。
ダンスは若い頃に踊っていましたが、しばらくやっていなかったためワークショップに参加するのが少し不安でした。ですが最初からすぐにダンスの振り付けを教わるのではなく、丁寧にウォーミングアップをしていただいたおかげで、楽しい雰囲気の中でダンスの振り付けを教わることができました。次回は違う曲にも挑戦したいです。
ライブ配信でワークショップに参加しました。インストラクターの指導がとても丁寧で、画面越しでもわかりやすかったので、安心してレッスンに参加できました。自宅にいながら普段動かしていない身体の部分を動かすことが出来たので、運動不足解消のためにまた参加したいと思いました。
「認知症フレンドリー講座」「リバイバルダンスワークショップ」をセットで申し込んだ場合の参考価格です。
参加人数や会場の場所によっては、合計額が異なる場合があります。詳細は見積依頼にてお問い合わせください。
合計
261,000円
10%オフ
290,000円
認知症
フレンドリー講座
140,000円
リバイバルダンス
150,000円
上記に加え、右記料金が発生します…機材配送費、著作権使用料、講師の移動にかかる交通費、宿泊費(必要な場合)など
参加者の感想
本人の立場にたつことの難しさを痛感すると同時に、その重要性にも気づくことができた貴重な体験だった。言葉では伝わりにくい本人の不安や恐怖、生活の困難さを疑似体験できるため認知症への理解が深まりやすいと思った。
見て聞いて学ぶことができる動画がありあきることなく学べた。認知症の人への対応をマニュアル的に覚えるのではなく、考え、感じ、接することが重要であると思った。
VR体験によって、認知症の人にはどのように見えているのか、私たちと同じ風景を見たときにどのように感じているのか、などがわかった。認知症の症状について、より具体的にイメージし、理解することができるようになった。